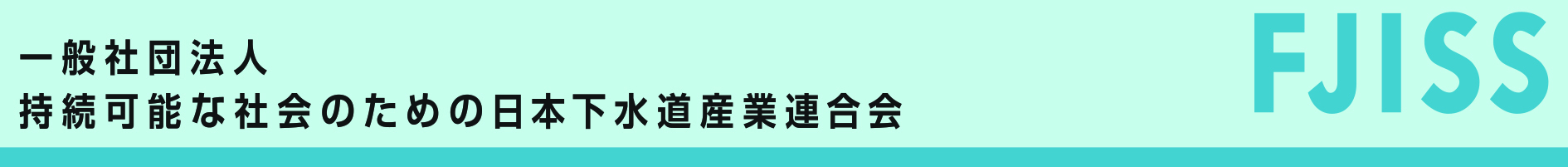
多様な業種が参画する(一社)持続可能な社会のための日本下水道産業連合会(FJISS、フジス)の活動報告を定期的に発信します。今回は下水道展’25大阪に併せて企画したセミナー(講演会)のもようを紹介します。

令和2年4月に設立されたFJISSは、下水道事業に関わる総合建設、専門土木、機械電気設備、資器材、調査設計、測量、管路管理、施設管理の計8業種が横断的に参加し、会員数は令和7年7月1日現在で62会員(正会員58社、賛助会員3社・1団体)にのぼっています。
FJISSは7月30日、下水道展’25大阪の併催セミナーを、インテックス大阪の6号館ホールGで開催しました。講師に元福島県三春町企業局長で前北海道大学大学院公共政策学研究センター研究員の遠藤誠作氏を招き、「下水道事業の持続可能性への挑戦」と題して講演いただきました。100名を超える多数の聴講者が参加し、講演終了後には聴講者との質疑応答も行われました。
遠藤氏は三春町において下水道経営の先進的な取り組みを行った第一人者で、現在は総務省の経営財務マネジメント強化事業アドバイザーを務めています。三春町で行った具体的な取り組みとしては、集合処理と個別処理を組み合わせた事業の効率化や、利用者負担の統一を考慮した下水道使用料の改定、下水道含む公営企業6事業すべてへの地方公営企業法の適用、事務や管理業務のアウトソーシング化などが挙げられます。

講演では、持続性に向けた問題点として、中小規模の自治体と大規模の自治体では経営問題への対応の仕方が違うため、同じ土俵で論じては策が出ないことなどを強調されました。小規模自治体はとくに厳しい財政状況を抱えており、コンサルタントなどに任せきりで、国や県の指示で行政事務をこなしているだけの主体性がない自治体が多いことを指摘し、「何でも業者に投げるのはよくない。基本方針は自ら立てるべき。仕事を受けたコンサルタントも達成感がないと思う」などと語られました。
このほか、「収益の大半を一般会計に依存する財政モデルはすでに破綻している」「事業の持続性を確保するには集合処理から個別処理へ転換する判断も必要」「下水道使用料の改定は負担格差の是正の観点で説明すべき」など、自らの経験を踏まえた持論やアドバイスを語られました。
編集・発行責任者(FJISS事務局長) 山本 哲彦