「上下水道の未来を考える対談シリーズ」第9回にあたる下水道の散歩道第75回は、田村憲久自由民主党社会保障制度調査会長をお訪ねし、お忙しい中、上下水道の未来像について、多岐にわたり、対談をさせていただきました(2025年6月3日収録)。
田村憲久先生とは、20年ほど前、私が国土交通省の下水道部長をしておりました頃、自由民主党下水道事業促進議員連盟の事務局長として、議員連盟をまとめておられ、連日のようにお伺いして、種々、ご指導をいただきました。その後も、日本下水道事業団理事長を5年強務めました際にも、大変お世話になりました。
また、2022年5月の、一般社団法人日本下水サーベイランス協会発足以降は、元厚生労働大臣のご経験を踏まえ、「感染症対策には、感染者数の実態把握に加え、下水サーベイランスを含めて、重層的な状況把握が必要。両者を併せた総合的な判断が必須。」との立場から、「下水サーベイランス」には、格別のご理解を頂いています。
現在、自由民主党社会保障制度調査会長の要職に在られ、上下水道関係では、自由民主党水道事業促進議員連盟会長、自由民主党下水道事業促進議員連盟会長も務められています。
今回は、「上下水道クライシス」とも言える上下水道インフラを巡る大変革のこの機に、上下水道のサステナブルな経営運営・下水サーベイランス・ウォーターPPP・環境対応強化等、「上下水道の未来像」について、幅広く、率直なご意見を聞かせていただきました。【谷戸善彦】

田村議員(右)と谷戸善彦氏。議員会館にて
田村憲久
自由民主党社会保障制度調査会長
元厚生労働大臣
自由民主党水道事業促進議員連盟会長
自由民主党下水道事業促進議員連盟会長
×
谷戸善彦
(一社)日本下水サーベイランス協会副会長
(公財)河川財団評議員
元国交省下水道部長
元日本下水道事業団理事長
[目次]
はじめに
Ⅰ.上下水道のサステナブルな経営・運営に向けて
上下水道インフラの費用負担論・国の支援のあり方について
上下水道会計の一体化について
上下水道インフラの広域化について
日本下水道事業団の存在
地域分散型上下水道システムの活用も
上下水道界における新技術活用の促進
Ⅱ.新たな財源確保の可能性
公共インフラのための予算を妨げる減税圧力
Ⅲ.下水サーベイランス
社会実装に向けて
管路腐食対策―新たな活用
Ⅳ.ウォーターPPPの今後
儲かる仕組み等の工夫・確立が必要
Ⅴ.EU下水道法を踏まえて
環境対応強化など前向きに検討すべき
おわりに
プロフィール
はじめに
谷戸 本日は、特に未来志向で、田村先生のお考えをお聞かせいただきたいという思いで参りました。
ご案内のとおり、現在、「上下水道クライシス」とも言える状態の中で、国土交通省からも、八潮陥没事故を踏まえた家田委員会の「第二次提言」や、「上下水道政策の基本的なあり方検討会」のとりまとめが動いています。本日は、「上下水道の未来像」として、上下水道一体化・国土強靭化・官民連携・下水サーベイランス等、いくつかのポイントに絞って田村先生の率直なご意見をお聞きしたいと思います。
最初に、「上下水道のサステナブルな経営・運営に向けて」について、お話を伺います。
Ⅰ.上下水道のサステナブルな経営・運営に向けて 
■上下水道インフラの費用負担論・国の支援のあり方について
谷戸 将来に向けて、水道・下水道のどちらもサステナブル(持続可能)な経営・運営が今後なされていくかが最大のポイントだと思います。そのためには、カネ・ヒト・モノが、必須です。カネは、更新・維持管理の財源、ヒトは、適切な運営のための官民の人材確保、モノは、サステナブル経営のための組織論です。
このうち、まず、「カネ」関連です。上下水道インフラの更新・維持管理の費用負担論・国の支援のあり方について、ご意見を頂けるでしょうか。
田村 下水道は老朽化が進む中で、ご承知の通り、更新に対して安定的な予算がなくて、数年前でしたか、当時の額賀会長の指示で、下水道事業促進議員連盟でPT(プロジェクトチーム)を立ち上げました。私が責任者でした。これから維持・更新していかなくてはいけない中、財源確保をという提言をしました。水道に関しましても、水道行政が国土交通省に移行し、災害対応への国庫補助の充実とともに、耐震対策・老朽化対策等の国土強靭化に対して、拡充の必要があると考え、動いてきています。
全て料金収入だけで、即ち、水道料金・下水道使用料だけでまかなってやれというのは、特に小さな自治体にはきついと思います。そういうことを考えると、やはり国が一定の役割というか、支援をしていかなくてはならない時期に来ていると思います。

谷戸 そうですね。下水道の雨水対策は、公費負担が位置付けられています。一方、水道及び下水道の汚水対策についても、公衆衛生の確保・国民の安全の確保・公共用水域の水質保全等、国費投入の一定の根拠が存在します。
今回の八潮の事故等も踏まえて、今、先生のおっしゃった「費用負担論・国の支援のあり方」の議論の進むことが期待されます。
田村 そうですね。「費用負担論・国の支援のあり方」の議論を国できちんとすべきと思います。
■上下水道会計の一体化について
谷戸 上下水道の一体化につきましては、国の行政組織としては昨年4月に国土交通省に水道行政が移管されました。
その中で、今後、上下水道関連のいろんな団体、組織の一体化や、各自治体での上下水道行政の一体化もあると思われますが、会計はどうでしょうか。水道の会計と下水道会計が将来的に一緒になるという発想もあるでしょうか。その辺りはいかがでしょうか。
田村 上下水道を見たときに、自治体が上下水道を両方とも持っているところと、持っていないところがあります。財務状況・規模の差等、自治体レベルで事情が大きく異なります。そうした中、会計自体の統合は、当座、現実的には難しいと思います。まず、水道は水道で、下水道は下水道で、持続可能な経営・運営に向け、改革を進めていくことが重要と思います。手段としては、広域化・人材育成・官民連携が鍵でしょう。その上で、将来は、会計の統合の検討に繋がるかもしれません。
■上下水道インフラの広域化について
谷戸 上下水道のサステナブルな経営・運営を考える時、広域化は、必須の手法と思います。広域化により、支出の効率化、人材の効率的運用、料金の均一化・低減等が期待できます。
広域化のスケールについて、お伺いします。広域化というときに、今、私たちは近くの市町村を巻き込むイメージです。県単位であるとか、もっと将来的には水道も下水道も、地方整備局単位とか、東日本・中日本・西日本の全国3エリア制とか、電力会社・高速道路会社のような、そういう姿が将来的にあるのか、ないのか、いかがでしょうか。
田村 上下水道は、超広域化をやったからといって規模の利益がどこまで出てくるかは、ちょっと疑問です。ただ、現在の近隣市町村同士ではなく、広域化のスケールが、最適な大きさになっていくことは必要だと思います。あまり大きくなりすぎると細かいところが分からなくなってしまうので、そういう意味では私はやはり、まずは、近くの自治体がある程度協力しながら広域化していくというのが、現実的な話だと思います。

谷戸 経営的・財務的にはそうですが、人材確保の深刻な問題がこれから起こると思います。中小市町村でなくても、今もすでに起こっていますが、上下水道関連の人材は、官側においても厳しくなると考えます。その際、大規模な広域化により、人材確保が可能となる可能性があります。
■日本下水道事業団の存在
田村 下水道の場合は日本下水道事業団(JS)という技術支援を行う仕組みがあります。
これは、大きいと思います。JSが水道も支援するという形があるような気がします。
今回、法律改正で、災害復旧支援に関してJSが水道事業に対応する制度ができました。突破口を作りましたので、将来的には水道事業の自治体の技術支援の役割をJSに担ってもらう可能性があるかもしれません。
谷戸 水道は浄水場とか配水池とか、そういった箱物が戦後、昭和20~30年代くらいに作ったものが、いま一気に改築更新の時期に来ています。水道も支援してもらいたいという、自治体からのJSへの期待は、大きいかと思います。
■地域分散型上下水道システムの活用も
田村 今回の八潮の陥没事故と昨年の能登半島地震でわかりましたが、これからは上下水道とも、地域分散型システムを、今まで以上に、効率的に活用すべきと思います。災害時の対応、復旧のスピード等の面も考慮して、適材適所で、位置付けるべきでしょう。
災害が非常に多い時期に入ってきました。今までの常識にとらわれず、予断なく、いろんな新技術を活用すべきと考えます。
■上下水道界における新技術活用の促進
谷戸 新技術の話が出ましたが、技術の宝庫と言える上下水道界の新技術の開発・活用についていかがでしょうか。
田村 どんどん、日本発の新技術を開発し、活用を図っていただきたいと思います。先日、管路腐食に強い抗菌剤の入ったヒューム管の話を聞きましたが、八潮の事故を踏まえ、今後は、抗菌剤の入ったヒューム管を標準にすることがあってもよいと思います。GXを考慮した、セメントを使わないコンクリートの採用も積極的に進めるべきでしょう。
国土強靭化の観点から、浸水対策関連技術も、大変、重要です。効率がよく、維持管理が容易で、設置しやすい内水対策用ポンプの開発・採用も期待されます。
八潮の事故を踏まえると、管路内、特に大口径の管路内の無人での点検・更新技術の更なる開発は、喫緊の課題と思います。水道技術の下水道事業での採用、下水道技術の水道事業での採用も、大事だと考えます。
谷戸 貴重なご意見、ありがとうございました。
Ⅱ.新たな財源確保の可能性 
■公共インフラのための予算を妨げる減税圧力
谷戸 新たな財源の話で突拍子かもしれませんが、東日本大震災の復興特別所得税(2.1%、期限2013.1.1~2037.12.31)の用途を拡大して(場合によっては、率も上げて)、公共インフラの老朽化・強靭化対策へ活用することは、難しいでしょうか。
上下水道だけではなく、日本のインフラ全体の、これからのマネジメントが大変だという中で、そういった発想はあり得ないでしょうか。八潮の陥没事故以前は、全く考えていなかったのですが、これだけの社会問題になり、国民の皆さんに公共インフラの老朽化問題が広く認識された今なら、ありうるのかなと思った次第です。
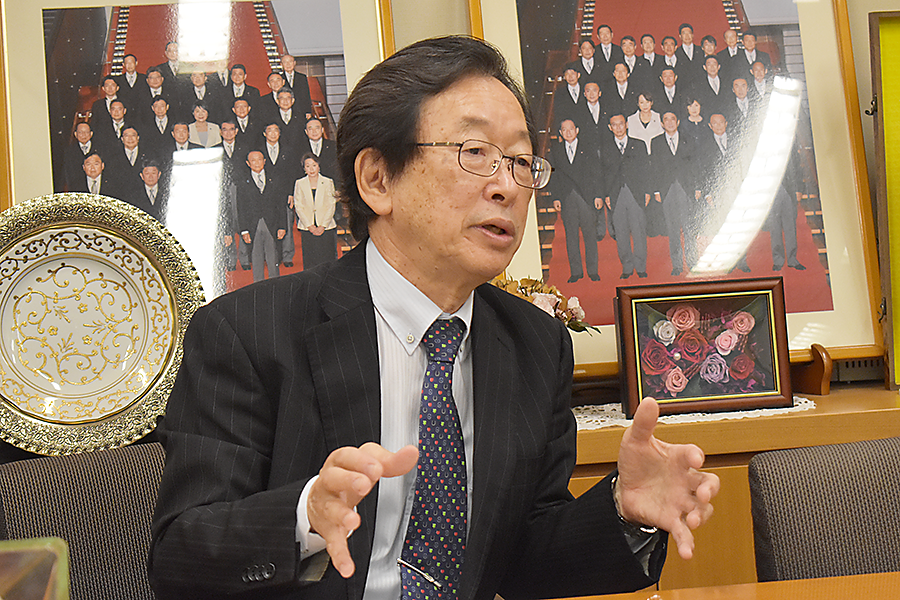
田村 今は、世の中、減税ですからね。国民は受け入れないのではないでしょうか。
谷戸 普通はそうですが、これだけの八潮の事故があったこのタイミングでも、やはり、難しいでしょうか。
田村 税収が上がっているのだから、そこから種々、出せと言われているわけです。
それを出さないから減税を国民から要求されています。上がっている税収を明確にこういう風に使っていますと宣伝できれば、こうも要求はされないでしょう。だから私は、補正ではなく当初予算から、公共インフラのための予算を付けるべきだと思っています。
財政当局も考えるといいと思います。減税圧力が強いとはそういうことだと思いますから。
谷戸 先生がおっしゃったように、当初予算で、今の公共事業全体で国費6兆円の壁を破れるか(当初予算の公共事業関係費はH26以降毎年6.1兆円)とリンクした話ですね。
田村 6兆円の壁の話も大きいと思います。実態では今、補正で組んでいる予算のうち、ほとんどはもう当初予算のように毎年予算化しているのですから、変わらないような気がします。私に言わせれば。やらない年はないですから。
谷戸 貴重なお話をありがとうございました。
Ⅲ.下水サーベイランス 
■社会実装に向けて
谷戸 下水サーベイランスについて、お伺いします。下水サーベイランスは昨年の「骨太の方針2024」で、「下水サーベイランスを含め、次なる感染症危機への対応に万全を期す」と、記述されました。田村先生のご支援に対し、本当に感謝しているところです。しかし、社会実装という、その次のステップになかなか、進んでおりません。
田村 厚生労働省が、感染症の実態を下水サーベイランスで重層的に把握するということにさらに前向きになることが大事だと思います。そうなってくれれば、国土交通省はのってきます。そのためには厚生労働省等への、感染症の現状把握・傾向把握における下水サーベイランスの有効性のアピールが、さらに大事だと思います。
谷戸 感染症対策としての下水サーベイランスが、重層的な手段の一つとして、極めて有効だという点について、田村先生のおかげもあって、厚生労働省さんにもここ2、3年でご理解いただきました。
■管路腐食対策―新たな活用
谷戸 新しい話として、八潮の陥没事故で、管路の腐食が話題になりましたのを踏まえ、管路の腐食予測に、下水サーベイランスを活用できないか、実証を始めています。管路の腐食はバイオテクノロジーの世界で、管路の中に、硫酸還元菌と、硫黄酸化細菌といった細菌がたくさんいると腐食しやすい。その細菌類も新型コロナウイルスの下水サーベイランスと同じように、処理場の入り口やマンホールで採水するとその濃度(細菌数)が判ります。管路が腐食していれば、腐食に悪さをする硫黄酸化細菌の数量に、きちんと差が出ます。
田村 下水サーベイランスのそういう使い方があるのですね。
谷戸 はい。日本の下水処理場は毎日のようにBODを測ったりしていますが、月に2回、重金属とかの詳細調査のための採水をやっています。その際、採水した水を使って、腐食に悪さをする細菌を測る。何カ月かに1回でもいいので、経時傾向を見る。また、他の処理場との比較をする。それにより、全国の下水管路の腐食危険度マップを作成できます。腐食対策のための下水道サーベイランスとなれば、下水道関係者は自分事となります。
田村 腐食危険度マップができて、その危険度に応じて、詳細調査を実施するといった形で活用できますね。
谷戸 こういうことを、いま始めています。うまく、動き出せば、感染症対策に関心のある自治体は、その採水した水を使って感染症対策としての下水サーベイランスも実施してもらうとよいと思います。こういうところから全国の処理場における下水サーベイランス体制の構築に繋げることができるとよいと考えています。
田村 よくわかりました。興味深いですね。
Ⅳ.ウォーターPPPの今後 
■儲かる仕組み等の工夫・確立が必要
谷戸 今後の官民連携において、ウォーターPPPは非常に大事です。先生としては、どういうふうに進めていったらいいとお考えでしょうか。
田村 ウォーターPPPは始まってまだそんなに間がありません。本当に企業に利益が出るのか。企業は利益が出ないとやらないですから、その仕組みをきちんと作っていかなくてはなりません。一方で自治体は、ウォーターPPPをやらないと、令和9年度より、管路改築の補助金がつかなくなります。現在、八潮の事故を受け、全国で、緊急の点検を5000キロ、やっています。その結果、危険な箇所となったところは、ウォーターPPPと関係なしに、ちゃんと予算をつけて改築する必要があると考えています。

谷戸 ウォーターPPPをやらなければ補助しないというペナルティ方式で、ウォーターPPPの促進を図っています。私は、今後は、ウォーターPPPをやるところは、優遇される、補助の範囲が広くなる、といったボーナス(優遇)方式の方が良いと思います。
田村 ウォーターPPPの第一ラウンドの終わる10年先を見据えて、その後、どうしていくのかということを考えなくてはならないと思います。民間は儲からないと参加しません。本当に儲かるための仕組み・事業運営期間を考える必要があるでしょう。
要するに、官というのは、基本的に利益を出してはいけないという発想です。
だから、官は、何をどう効率化して利益を出すようにするかという努力がしづらい。民は株主にも還元しないといけないので、利益を出さなくてはならない。そういう意味では、民は、官では思いつかないような効率化も含めたいろんな手法を考え出してくれます。
民の方には、いろんな知恵を出していただきたいですね。10年の第一ラウンドが終わって、「もうやめた」と言われたら終わりですからね。そうならないように、仕組み等の工夫・確立が必要です。
谷戸 そうですね。これからの動きが大事ですね。ご意見、ありがとうございました。
Ⅴ.EU下水道法を踏まえて 
■環境対応強化など前向きに検討すべき
谷戸 最後にお伺いします。「EU下水道法(EU指令)」というものがあります。EUは、本当に、先を行っています。今後のあるべき水質環境と下水処理のあり方等に関して、3、4年間、EUの中で検討してきた法案が、昨秋、EU議会で可決され、今年の1月1日から発効しています。
その中で、3次処理を超えた「4次処理」を提案しています。それから、脱炭素(脱CO2)関連で、処理場のエネルギー自立化を各国内合計単位で、義務付けました。さらに下水サーベイランスも義務付けました。重要な点は、環境に係る法律の中で決めたのではなく、下水道法の中に位置づけた点です。
日本もすぐにとはいかないにしても、できるだけ、早く、環境対応・CO2対応・下水サーベイランス対応を下水道法の中で、位置付けるべきと考えます。
田村 4次処理とはすごいですね。窒素・リン除去等の3次処理以上の処理ということですね。
谷戸 はい。3次処理は窒素、リン除去が主ですが、4次処理は微量有害有機物質の処理です。処理方式は、技術的には、既に、確立しています。
もう一つ特徴的なのは、4次処理の費用負担者です。EUはその4次処理分のプラスアルファ分(汚濁物質負荷増分)を下水道等に一番多量に出しているのは製薬会社と化粧品会社であると特定できていることから、4次処理分の増加費用は、化粧品会社と製薬会社から取ると決定しています。
下水道の処理区の中にあり、その微量有害有機物質を下水道に放出している製薬会社の工場・化粧品会社の工場等に負担してもらうということです。
田村 なるほど。大変、先進的な取り組みですね。我が国も、今後、前向きに検討すべきと思います。
おわりに 
谷戸 日本も、これから、老朽化対策等、目の前の課題への対応だけでなく、未来を俯瞰して、環境等の重要政策を先取りすることが、大事だと思います。本日は、大変お忙しい中、お時間をいただき、貴重なご意見を頂き、本当にありがとうございました。
プロフィール
田村憲久(たむら・のりひさ)氏
1964年生まれ。1996年衆議院議員初当選。厚生労働大臣政務官、文部科学大臣政務官、総務副大臣、厚生労働大臣(第16代、第23代)、などを歴任。現在、自由民主党社会保障制度調査会長。自由民主党水道事業促進議員連盟会長、自由民主党下水道事業促進議員連盟会長、日本下水サーベイランス協会特別顧問等も務める。
谷戸善彦(やと・よしひこ)氏
建設省入省。1987年西ドイツカールスルーエ大学客員研究員。その後、京都府下水道課長、国土交通省東北地方整備局企画部長、同下水道事業課長、同下水道部長、日本下水道事業団理事長、㈱NJS取締役技師長兼開発本部長等を歴任。現在、一般社団法人日本下水サーベイランス協会副会長、公益財団法人河川財団評議員等を務める。